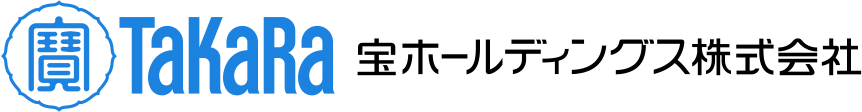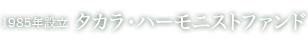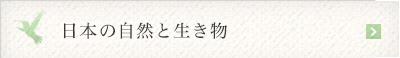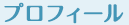2016.03.30
2016年1月下旬にNPO法人 藤前干潟を守る会を訪問し、理事長の亀井浩次さんに 藤前干潟について、また会の活動内容についてお話を伺いました。
藤前干潟とは?
この日、亀井さんにお話を伺うため訪れたのは藤前活動センター。眼前には、潮が最も引いた時には238haという広大な藤前干潟が広がります。藤前干潟は、愛知県名古屋市の海に面したエリアー伊勢湾最奥部で、愛知県西部の庄内川、新川、日光川3河川が合流する河口部に位置します。ここは日本有数の渡り鳥渡来地としても知られ、亀井さんは「オーストラリアなどからやってくる渡り鳥の一種、コアジサシの繁殖地でもあり、トビハゼやチゴガニなど、干潟にしか生息できない貴重な生き物がたくさん生息しています」と教えてくれました。
 コアジサシ
コアジサシ コアジサシの卵
コアジサシの卵 トビハゼ
トビハゼ.jpg) チコガニ
チコガニ
そもそも干潟とは、川から運ばれた土砂がたまってできる砂泥地のこと。「干潟には、水中の養分と太陽の光、それに空気(酸素)と生き物に必要な要素が全部そろっています。そのため植物プランクトンが育ち、それをカニや貝、小魚たちが食べ、さらにそれらを鳥がエサにしています。ここで食物連鎖がバランスよく成り立っているのです」

活動のきっかけはゴミ埋め立て問題
生き物たちがたくさん住んでいる干潟のある「内湾の河口部」は、実は大きな街ができる条件とも一致します。そのため、高度成長期には工業地帯として多くが埋め立てられ、全国にあった干潟の約40%が消滅したといわれています。そんな危機的状況にありながら、名古屋港の臨海工業開発の中でも奇跡的に残ったのが、ここ藤前干潟なのです。
「藤前干潟を守る会」は、1987年、名古屋市の廃棄物最終処分場建設計画から干潟を守るために活動を開始しました。その後、15年にわたる保全活動が実って計画は中止。現在、藤前干潟は国際的にも守られるべき湿地として、ラムサール条約にも登録されています。「計画が中止になった後、名古屋市はゴミを減らす政策に転換。会の活動は、名古屋市が環境先進都市を目指すきっかけになったと自負しています」と亀井さんは話します。
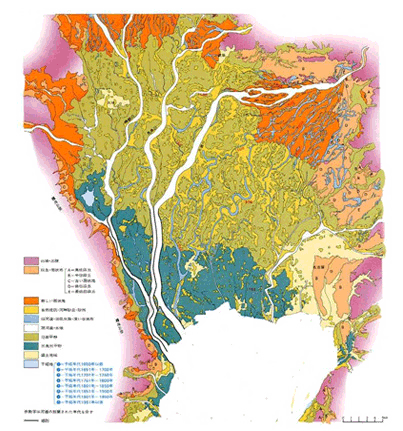 名古屋港原地形
名古屋港原地形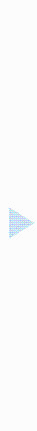
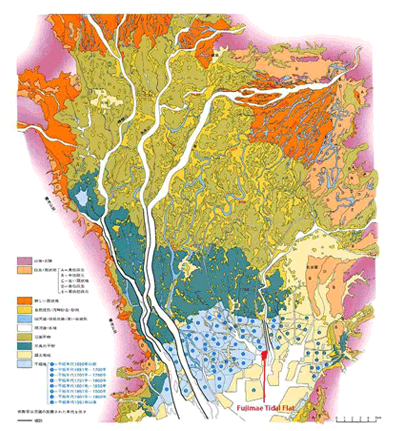 名古屋港現地形
名古屋港現地形
「藤前干潟を守る会」の取り組みとは
現在、「藤前干潟を守る会」は藤前干潟とその流域をフィールドに生き物や環境を保全する活動を展開しています。活動内容は、干潟の保全活動や調査・研究、環境教育、普及活動と大きく分けて4つ。いろいろある活動の中でも亀井さんが特に大切にしていること、それはいろいろな人に干潟について知ってもらうことだと言います。そのため「藤前干潟を守る会」では、干潟に詳しいガイド「ガタレンジャー」を養成する講座や、小学4年生~中学生を対象とした子ども向け環境学習プログラムも実施。子どもたちはもちろん大人にとっても、普段はなかなか触れることのない生き物について知ることで視野が広がり、生態系に興味を持ち、干潟が直面している問題から自然環境など、いろいろな問題に目が向くようになると言います。


これからの課題、目指していくこと
保全活動が実を結んだように見える一方で、「藤前干潟だけが保全されることがゴールではない」と亀井さんは考えています。「例えば、近年では藤前干潟に来るコアジサシが激減している問題があります。これは、干潟周辺の環境の変化も大きく関わっており、藤前干潟の保護の継続、ひいては伊勢湾全体の自然保護、環境改善のための活動が大事になってくると思います」と亀井さん。全国にある干潟保全にも取り組んでいくため、各地の干潟保全活動をしている団体とも交流を深めるなど、名古屋だけにとどまらない全国区へと保全の輪は広がっています。
.jpg) 沖縄・泡瀬干潟との交流視察
沖縄・泡瀬干潟との交流視察 宮城・蒲生干潟との交流視察
宮城・蒲生干潟との交流視察
干潟保護に貢献しているタカラ・ハーモニストファンド助成先
-
(平成23年度助成)NPO法人 藤前干潟を守る会
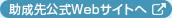
「干潟を取り巻く豊かな自然を守るために 」
」
-
(平成21年度助成)NPO法人 日本国際湿地保全連合
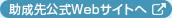
「市民参加型干潟調査手法の普及と調査の実践」