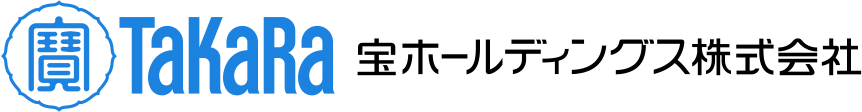日本食を米国に浸透させてきた先駆者が目指す 新しい日本食文化の創造
2025/01/31
<目次>
ミューチャルトレーディング4代目社長が、寿司バー普及のきっかけに
-
ミューチャルトレーディング(以下、MTC)はロサンゼルスで1926年に設立された。もうすぐ100周年を迎える老舗企業である。もともとは日系食品小売店10店舗が共同出資し、当時は在米日系人向けの食材輸入会社としての役割を担っていた。
「日本食を通じて日本の文化を普及する」という一貫した理念を基盤として日本食普及の先駆者として事業を展開してきた。
MTC本社外観(ロサンゼルス)1971年には宝酒造から純米酒(「デラックス松竹梅」)の輸入を開始するなど宝グループとの取引がその後も長く続き、2016年に宝酒造インターナショナルグループ(当時は宝酒造)に参画した。北米に日本食文化を普及するという理念の一致が両社を引きつけ合ったからである。そのパイオニアぶりをMTCの大畑正敏社長はこう語る。
「当社の4代目社長となる金井紀年(かないのりとし)が60年代にロサンゼルスで寿司文化を紹介した第一人者なのです。日本食と言えばまだ、すき焼き・天ぷらぐらいだった時代に、金井があるアメリカ人と知り合ったことがきっかけでした。その人は日本で食べた寿司をいたく気に入り、アメリカでも流行るはずだと確信し、リトルトーキョーでカウンターだけの小さな寿司バーを開店しようと言い出したのです。金井がそれに協力し、結果的に65年にオープンした『川福』につながり、アメリカ最初の本格的な寿司屋となりました。以降、大都市に寿司バーが広がる契機になりました」 MTC 大畑社長
MTC 大畑社長とは言え当時はまだ生魚や海苔が苦手な人たちも多く、アボカドやサーモン、マヨネーズを使ったカリフォルニア巻きなどが生まれ、形を変えながら広がっていった。海苔を隠すためにバックロールというシャリを表に出す裏巻きも登場した。時代は移り、今では表巻きの手巻き寿司が流行り、ONIGIRI(おにぎり)も人気となっている。

カリフォルニアロール
ラーメンのスープと麺を提供し、ラーメンブームの火付け役に
-
現在、アメリカで大人気のラーメンの普及にもMTCが一役買っている。 「10年以上昔の話ですが、京都にある調味料メーカーが米国でのラーメンスープの販売に興味があることを知り、当社は先方と提携することにしました。」(大畑社長)
また当時、あるアメリカの製麺メーカーが、2004年にロサンゼルスに工場を建設していたことから、MTCは同社とも提携、スープと麺を合わせて提供し始めた。
「店主がスープと麺を自分で作るのは大変ですからね。当社は現地のニーズに応じて日本などからあらゆる食材を仕入れるルートがあり、市場に食材を提供することでラーメンという日本食も普及し始めたのです」(大畑社長)
以降、ラーメンは西海岸から東海岸にも拡大していった。その背景にはMTCがスープや麺、どんぶりなどもワンストップで提供するサービス体制と販路を全米に持っていたこともある。ただし、ラーメンがいま流行しているとは言え、現地には、麺をすするのが苦手な方や、ネコ舌の方も多いため、日本のように短時間で食べるのではなく、じっくりと時間をかけることが多い。MTCでは、日本流を押しつけることなく、ファストフードではなくサイドメニューを充実させ、ディナーとしてゆっくり楽しめるような現地の嗜好に沿う提供方法を提案してきた。
今も現地ニーズを先取りして対応する姿勢は変わらず、例えば手巻きや細巻き寿司人気も素早く察知して、現地の嗜好に合わせた具材や専用のテイクアウトボックスなどを顧客に提案している。
高級寿司店ではメニューをシェフに一任する「おまかせ」が広まっており、ウニやマグロなど日本の高級ネタを求める顧客も増えてきた。そこでMTCでは2024年10月に豊洲市場内にある仲買「築地太田・オータフーズマーケット」をグループに加え、高品質な鮮魚をアメリカに安定的に供給する体制を整えた。航空便で新鮮さを保ったまま、ニューヨークのレストランに届ける仕組みを持っている。
築地太田「食材の提供だけでなく、ワイン文化のように食事と酒類のペアリングにも力を入れています。サケ・アドバイザーの資格を持つ営業がメニューに合わせた酒類を提案します」
日本酒・ビールに加えて、現在、焼酎の普及にも力を入れている。カリフォルニア州やニューヨーク州ではアルコールが24%以下であればレストランにおいてビア・ワインライセンスで提供が可能になった。より多くの日本食レストランで焼酎やチューハイを楽しめる下地が整ったわけだ。国内の宝酒造には「タカラcanチューハイ」や 「タカラ焼酎ハイボール」などの人気商品があり、海外事業を担う宝酒造インターナショナルでは昨年来、米国専用の缶チューハイ「Takara CHU-HI」のレモン・リンゴ・ピーチ味の輸出を開始した。
「様々な商品を紹介することで、アメリカにおける焼酎全体の認知度の向上、市場拡大につながる事を期待しています。」(大畑社長)
米国専用のTaKaRa CHU-HI(左から、レモン、アップル、ピーチ)
日本食シェフの養成学校を開校
-
日本食レストランが増加する中で、シェフの育成が課題となってきた。日本食は生の魚介類を使うので、特別な調理技術や衛生管理の知識が必要となる。そこで、MTCは2008年に「MIYAKO SUSHI & WASHOKU SCHOOL」の前身となる料理学校を開校した。
日本人の現役シェフが約1ヶ月間で基本的な技術や日本食の歴史・文化・哲学も教える。参加者の多くは日本食を作ったことがない生徒だが、プロのシェフへの入口として支持されている。さらに学びたい人には、より高度にアレンジされた和食のメニューを学ぶなどのコースも用意している。
MIYAKO SUSHI & WASHOKU SCHOOLまた、2010年には和酒のスペシャリストを育成するために「Sake School of America」を開校した。日本酒だけでなく、焼酎やリキュールなど日本のアルコール飲料全般を学ぶため、日本の酒類研究機関やワインの教育機関とも連携し、世界中でクラスを開講したり、酒類コンペティションへの参加なども行っている。2024年度は400名超が受講した。
「MIYAKO SUSHI & WASHOKU SCHOOL」の卒業生には日本食レストランを立ち上げた人も少なくない。MTCが全面的に支援して、卒業生がロサンゼルスで始めた「Yunomi(湯呑み)」という手巻き寿司店は成功を収めて、3年以内に3店舗目を展開している。
Yunomi(湯呑み)で提供されている手巻き寿司
米国最大規模の日本食レストランショーを開催
-
同様に日本食普及のため、1989年から「Mutual Trading Japanese Food & Restaurant Expo」(以下、JFRE)という米国最大規模かつ最長の歴史を誇る日本食レストランショーを開催している。毎年9月にはニューヨークとロサンゼルス、ホノルルで開催し、日本食関連・酒類・レストラン用品・雑貨などのサプライヤーが出展、日本食関連の経営者・シェフ・外食産業関係者を招いている。

MTCとサプライヤーの皆様との集合写真2024年9月にロサンゼルスで開催されたJFREには過去最高の2600人が来場、140以上のブースが軒を連ねた。特に和牛とマグロのブースが盛況で、簡単に調理できるラーメンや牛丼などの加工食品にも注目が集まった。
「日本食は“ブーム”という時代は過ぎて、“食文化”として定着しています。今後は、現在拡がっているレストランだけではなく、日常食として米国の家庭の食卓にも浸透させていくことを目指します」と大畑社長は抱負を語っている。
「和牛」ブース

「大トロ・マグロ」ブース
酒器と和酒のペアリングで味わいが変わることを発見
-
JFREは当初、食器市としてMTCの倉庫駐車場を使って、食器の特売、試食や新商品の発表、レストラン関係者の交流の場としてお祭り的に始まった。そこから年々、来場者が増え、コンベンションセンターに会場を移して本格的な展示会に拡大した。現在では海外における日本食B to Bの展示会として最大規模である。
「JFRE2024のセミナーでは『酒器による日本酒の変化』をテーマに実際、試してみました。4種類の酒器を用意し、同じ日本酒で飲み比べしてみたのです。すると驚いたことに酒の味わいが本当に変わりました。ワインも種類によってグラスを変えますが、日本酒も同じであることに気づき、今後は食材と食器、酒器と和酒のペアリングを考えてお客様にご提案できたらと考えています」と大畑社長は語る。
日本国内でも清酒と酒器の関係まで踏み込んで提供している店は少ないが、ワイン文化で育っている欧米人には逆に当たり前のことかもしれない。MTCの活動を通じて新たな和酒文化も生まれつつある。
酒器の違いによる飲み比べ体験JFREでは和包丁の研磨サービスも実施、アメリカのシェフたちの注目を集めた。
「日本食以外にも和包丁は広がっており、日本の包丁文化を伝えると共に、日本の包丁職人とシェフたち専門家同士をつなぐ役割も果たしていきたい」と大畑社長は語る。
食材や料理だけでなく、酒器や調理器具も含めた「日本の食文化」はMTCの事業を通じて確実にアメリカ社会に浸透している。
大畑社長は、米国での日本の食文化の浸透は、日本の食文化の進化・発展につながっているとし、「アメリカ市場への提案の中で生まれた、新しい日本食のアイデアが、日本へ逆輸入したり、世界に発信されたりして定着していく。そんな日本食文化のイノベーションにチャレンジしていきたい」と意気込む。