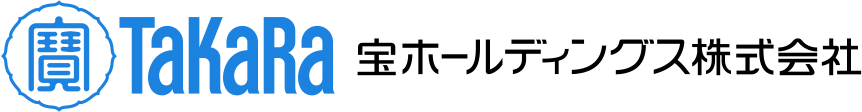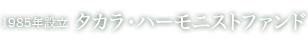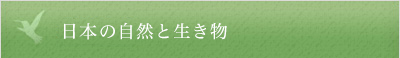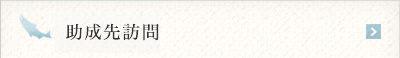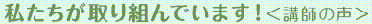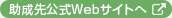2016.03.30
日本の砂浜は重要なウミガメの産卵地

海岸で実際にウミガメを見たことがあるという人は少ないかもしれませんが、ウミガメは「浦島太郎」にも登場するなど、昔から日本人になじみの深い生き物です。世界に7種(8種とする意見もある)いますが、今そのすべてのウミガメが絶滅の危機に瀕しています。日本では5種のウミガメが見られ、そのうちアカウミガメ(福島県から沖縄県)、アオウミガメ(小笠原諸島や南西諸島)、タイマイ(沖縄県)の3種は、産卵のためにメスが砂浜に上陸します。中でも、アカウミガメは北太平洋では日本の砂浜を唯一の産卵地としています。
日本生まれのアカウミガメ、太平洋を渡る

日本の砂浜で生まれたウミガメは、その後どのような一生をたどるのでしょう?ウミガメは一生のほとんどを海中で過ごすため調査が難しく、わかっていないこともたくさんありますが、ここではアカウミガメを例に見てみましょう。
砂の中で卵から生まれた子ガメは、夜になって涼しくなるのを待って地表に這い出し、物陰を避けて水平方向に遮蔽物のない海に向かって歩き出します。そして、子どものうちに黒潮に乗って日本を離れ、太平洋を横断し、アメリカの西海岸やメキシコのカリフォルニア半島へと渡ります。約1万キロメートルもの距離を横断するのにかかる時間は、約5年。その後、現地で17年くらい過ごしたのち、日本へと戻ってきます。東シナ海などの浅い海底で貝やヤドカリなどを餌にするか、外洋の表層でクラゲなどを餌にするかして、40歳くらいになってようやく産卵します。産卵の季節は主に春から夏にかけて。卵の準備ができたメスは、夜になると用心深く砂浜に上陸して、海浜植物が生えている付近に後ろ脚を使って深さ50-60cmの穴を掘り、その中に卵を産み落とします。
ウミガメを守ろう! 大きな責任を負う日本

世界的に絶滅が危惧されているウミガメ。食料や装飾品目的での乱獲、魚を獲るための網や釣り針に間違ってかかることによる溺死、産卵と卵の発生に適した砂浜の減少や、ウミガメの生態を無視した間違った保護活動など、様々な要因があげられます。
四方を海に囲まれた日本は、昔から漁業をはじめ、生活・文化・産業等、様々な形で海と深い関わりを持ってきました。このことは、ウミガメ保護においても、日本は大きな役割と責任を負っていると言えます。
日本には、ウミガメ保護に取り組む人々や団体が多くありますが、タカラ・ハーモニストファンドではこれまでにウミガメ保護に取り組む下記の団体へ支援を行ってきました。ウミガメ保護活動団体などのホームページでは、ウミガメに関する話題がたくさん紹介されています。興味を持たれた方は、是非こちらもご覧ください。
ウミガメの不思議
【陸から海へ…ウミガメの進化】
ウミガメは陸の上で進化して、海に戻った生き物。そのため陸で暮らすリクガメとは違って、海で泳ぎやすいように手足はひれ状に、甲羅は薄くかつ扁平でツルッとしているのが特徴です。そのため、リクガメのように手足を甲羅にしまうことができません。
【温度依存性決定】
ウミガメの性別は砂浜の温度によって決まる「温度依存性決定」という特徴があります。29℃から30℃を境に砂の温度がそれよりあたたかいとメスの割合が高まり、それより低いとオスが増えるのです。
日本で生まれたアカウミガメはどうして太平洋を横断するのか、寿命は何歳までなのか…他にもまだまだ不思議なことがたくさんあります。下記のウミガメ保護活動団体などのホームページでは、ウミガメに関する話題がたくさん紹介されています。興味を持たれた方は、こちらもご覧ください。
ウミガメ保護に貢献しているタカラ・ハーモニストファンド助成先
-
(平成13年度助成)NPO法人 日本ウミガメ協議会
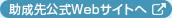
「一般市民と共にウミガメの保全に取り組む 」
」
-
(平成2年度助成)NPO法人 屋久島うみがめ館
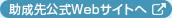
「屋久島、永田、田舎浜におけるウミガメの産卵生態調査」