2017.03.14
木の岡ビオトープ自然観察会 ~琵琶湖の湖畔で自然とふれあう~
おにぐるみの学校
2016年12月4日(日)、滋賀県で活動する『おにぐるみの学校』が「木の岡ビオトープ自然観察会」を開催しました。
琵琶湖沿いの自然豊かな地で、地元の小学生や親子がどんな風に自然と親しんでいるのか、宝酒造が実際にお邪魔して一緒に体験させていただきました。
その内容をお伝え致します!
「木の岡ビオトープ」と『おにぐるみの学校』ってなんだろう?
今回訪れた「木の岡ビオトープ」は、琵琶湖の西岸、滋賀県大津市木の岡町にあります。琵琶湖に面しているため、陸地から水辺までさまざまな自然が混在しており、実に多種多様な生物が生活する貴重な場となっています。この良好な自然環境を保全し、環境学習などのフィールドとして活用するため、地域住民や専門家、学校・企業・行政が一緒になって平成17年に『おにぐるみの学校』が設立されました。この『おにぐるみの学校』では子どもも大人も共に参加できる多彩な活動に取り組んでいます。
 平成15年に滋賀県が実施した調査で、植物だけでも約340種が確認されている「木の岡ビオトープ」
平成15年に滋賀県が実施した調査で、植物だけでも約340種が確認されている「木の岡ビオトープ」 水辺特有の植物が生育するゾーン。
水辺特有の植物が生育するゾーン。
湿地の向こうに見えるのが琵琶湖です。
市街地の中に豊かな自然!?「木の岡ビオトープ」が存在する謎とは…
昭和43年頃、国道161号線の東側にホテルが建設されました。しかし、その後会社が倒産し廃墟となってしまいます。
このビルは「幽霊ビル」と呼ばれ、人があまり近づかなくなり、廃墟となったホテルから琵琶湖側は人の手が入ることはありませんでした。このおかげで、長い長い年月を経て現在の自然豊かな状態となったというわけです。そして、この幽霊ビルは平成4年に撤去され跡地は草原となりました。これらの自然は、現在「おにぐるみの学校」による保全活動によって守られ残されています。
水鳥観察会
この日の自然観察会は「水鳥観察会」からスタートです。1年中琵琶湖にいる野鳥や水鳥のほかに、12月は寒い地域から飛んでくる渡り鳥もいて、この時期は水鳥を観察する絶好のタイミング。毎年やってくる渡り鳥に加え新たに飛来する鳥もいて、同じ時期に観察しても見られる鳥は違うといいます。さて、今日はどんな鳥に出会えるのでしょう。
 ガイドは鳥類を専門に研究する濵田知宏先生。
ガイドは鳥類を専門に研究する濵田知宏先生。
双眼鏡の使い方を習ったら森の中へ。 目を閉じて周りの気配に耳を澄まします。
目を閉じて周りの気配に耳を澄まします。
すると鳥の鳴き声が耳に飛び込んできます。 「あ! あっちからギィーギィーって聴こえた!」
「あ! あっちからギィーギィーって聴こえた!」
「双眼鏡で見えるかな?」 黄色く太いくちばしの鳥「イカル」を発見!
黄色く太いくちばしの鳥「イカル」を発見!
後半は森の中から少し移動して、琵琶湖のそばで水鳥を観察しました。
 望遠鏡で遠くにいる水鳥を観察中。
望遠鏡で遠くにいる水鳥を観察中。 カルガモ、オオバン、滋賀県の鳥「カイツブリ」を発見!
カルガモ、オオバン、滋賀県の鳥「カイツブリ」を発見!
ヨッシーの自然教室
つづいて、ヨッシーこと辻田良雄先生による自然教室です。生き物の身体の一部が描かれたカードを見て、それがどんな生き物なのかを当てる動物クイズをしたり、色とりどりのモールを使ってアメンボを作ったり。頭と体をめいいっぱい使って、自然について学びました。
 「この森には鳥のほかにどんな生き物がいるかな?」
「この森には鳥のほかにどんな生き物がいるかな?」
ヨッシーの質問に元気よく答える子どもたち。 動物クイズはチームに挑戦!
動物クイズはチームに挑戦!
みんな輪になって中央にあるカードを取りに行きます。 カードには「木の岡ビオトープ」にいる動物の
カードには「木の岡ビオトープ」にいる動物の
身体の一部が描かれています。 最後にみんなでカードを見ながら答え合わせ。
最後にみんなでカードを見ながら答え合わせ。
ネズミ、蟻、蛾、リスのカードがありました。 琵琶湖にたくさん生息するアメンボを、
琵琶湖にたくさん生息するアメンボを、
モールを使って作ります。 仕上げに目玉をつけたらカラフルなアメンボの完成!
仕上げに目玉をつけたらカラフルなアメンボの完成! 最後は作ったアメンボを浮かせる実験。
最後は作ったアメンボを浮かせる実験。
ドキドキしながら「ちゃんと浮くかなぁ」
豚汁の試食
いっぱい学んだあとはお待ちかね、豚汁の試食タイムです。水鳥観察や自然教室でネイチャーゲームをしている間に『おにぐるみの学校』のスタッフの人が準備をしてくれていました。熱い豚汁が外で冷えた身体をやさしく暖めてくれます。
 大きな鍋2つにたくさんの豚汁。
大きな鍋2つにたくさんの豚汁。 味の決め手はたくさんのサツマイモです。
味の決め手はたくさんのサツマイモです。 熱々の豚汁をフーフーしながらいただきます。
熱々の豚汁をフーフーしながらいただきます。 最後に参加者全員で記念撮影。
最後に参加者全員で記念撮影。
みんないい笑顔でパシャリ。
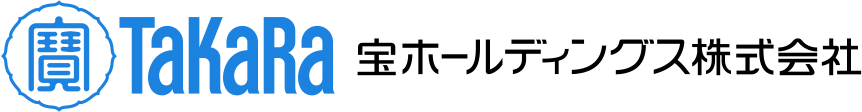


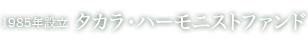


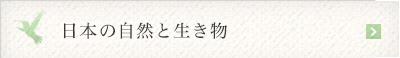


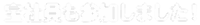
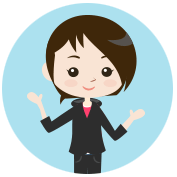 木の岡ビオトープは一歩、敷地内に入ると、すぐ近くを国道が走っている市街地とは思えないほど本当に自然が豊かな場所でした。
木の岡ビオトープは一歩、敷地内に入ると、すぐ近くを国道が走っている市街地とは思えないほど本当に自然が豊かな場所でした。

