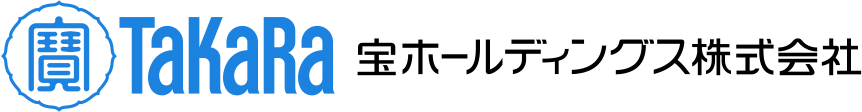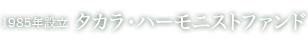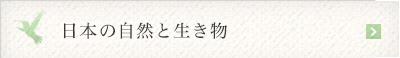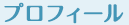2019.03.27
里山の竹林整備に取り組む鹿背山倶楽部
 もとあった田畑に竹や雑木が侵入している、当時の里山の様子
もとあった田畑に竹や雑木が侵入している、当時の里山の様子万葉の時代から親しまれてきた里山を再生
京都、大阪、奈良の3府県にまたがる京阪奈丘陵。
けいはんな学研都市として変貌を遂げてきた一方で、今なお豊かな自然が残る地域でもあります。鹿背山の里山一帯は、京都府木津川市の市街地から程近い場所にあり、宅地開発計画の変更により放置されて荒廃が進んだという経緯があります。そこで、2005年にUR(都市再生機構)に在籍していたメンバーらが母体となり、里山としての保全と活用を目指し発足したのが鹿背山倶楽部です。
 けいはんな学研都市の木津川市に位置する鹿背山
けいはんな学研都市の木津川市に位置する鹿背山現在、代表を務める菅野伸也さんは、「このままではいけない。里山再生によって自然環境を守り、地域住民の活動と交流の場にしていこうという強い思いがありました」と話します。
当時は、竹や雑木がいたるところに生い茂り、足を踏み入れるのも困難な状況だったとか。
菅野さんに、約10年前から伐採によって整備を進めてこられた一角を案内してもらいました。以前は荒れた竹林だったとは思えないほど。ナラ、桜、栗など多様な雑木が適度な間隔で茂り、散策も楽しめる明るい里山林として再生されています。しかも、雑木は人が植えたわけではなく、鳥や動物が種子を運んできて自然に生えてきたものだというから驚きです。
人が適正に手を加えることで、自然の持つ力がバランスよく生かされることが見事に証明されていました。
 整備が進んだ里山林らしい風景
整備が進んだ里山林らしい風景 伐採した竹を活用した小屋とビニールハウスの休憩所
伐採した竹を活用した小屋とビニールハウスの休憩所

そもそも、里山林は、伐採して薪や炭などの燃料を得たり、下刈りや落葉掻きによって肥料を得たりと、人の手が加わり続けることで成り立ってきました。そのため、自然の森と異なり、単に放置するだけではバランスが崩れ、良い森にならないケースが多いのです。
よみがえった里山に、生き物が帰ってくる
里山としての再生が進んだことで、徐々に様々な生き物も帰ってきています。
2017年には、京都府環境部自然環境保全課から「カスミサンショウウオ保全回復事業」の認定も受けています(カスミサンショウウオは環境省のレッドデータリストで絶滅危惧種に指定)。 明るくなった里山林には、オオタカ、フクロウ、シジュウカラなどの鳥類も飛来し、生き物たちが息づく豊かな自然環境が着実に育っています。
野生の生き物の存在を身近に感じる里山。そこでは、こんなエピソードも。
ある日、菅野さんが、数匹の子ウサギがヘビに狙われていたところを助けたことがありました。可愛らしい子ウサギに目を細め無事を喜んでいたのですが、数日後、ウサギが畑の作物をことごとく荒してしまったというのです。とっさにヘビの頭を叩いて死なせてしまったことを思い出し、生き物の世界に人間が手を加えることの影響を考えさせられるきっかけとなったそうです。以後は、農作物を荒らされないための防御や駆除は行うものの、「可哀そうだと感じるから」という理由だけで、人が自然のバランスを崩すことはしないように心がけているのだとか。

 カスミサンショウウオの幼生
カスミサンショウウオの幼生 地面に産み付けられた野鳥の卵
地面に産み付けられた野鳥の卵
繁殖を続ける竹林の整備が最大の課題
宝ホールディングス社員が、竹林の整備に参加しました!
 急斜面で作業を手伝う宝ホールディングス 社員
急斜面で作業を手伝う宝ホールディングス 社員鹿背山を里山として再生するうえで、最も困難かつ基本的な取り組みとなるのが荒れた竹林の整備だということで、今回は整備を続けている中の、まだ手つかずの竹林の伐採に参加させていただきました。
竹林に入っていくと淡竹(はちく)が極端に密集し、幹が重なるように繁茂している様子に圧倒されました。25平方メートルごとに10本程度を残して間伐するそうです。気が遠くなるような印象さえありましたが、ベテランのメンバーの方たちは、急斜面の足場にもかかわらず、のこぎりを使って次々と手際よく伐採を進めていきます。 私は山を登るだけで息切れしてしまいました。
そんな状態で急斜面でのこぎりを使う作業は危険なため、私は伐採した竹を下す作業のお手伝いをさせていただきました。10メートル以上の竹を持って、竹林の間を縫って降りるにはルート選択が必要で、途中で何度も立ち止まることとなりました。急斜面の登り降りを繰り返すと、12月初旬の寒さの中でしたが、すぐに汗びっしょりになりました。
メンバーのみなさんは、伐採した竹を斜面から降ろすと、今度はどんどん枝を切り払っていきます。あっという間に綺麗に積まれていく様子は圧巻のひと言でした。実際に現地の作業に参加してみて、体力と技術、そして何よりも人手が必要なことを痛感しました。
 放置され幹が重なるように繁茂している竹林
放置され幹が重なるように繁茂している竹林 25平方メートルごとに10本程度を残し、のこぎりを使って手際よく間伐
25平方メートルごとに10本程度を残し、のこぎりを使って手際よく間伐 伐採した竹を斜面から下ろす
伐採した竹を斜面から下ろす 下した竹は枝を切り払っていく
下した竹は枝を切り払っていく 要領よく集められ綺麗に積まれた竹
要領よく集められ綺麗に積まれた竹
菅野さんによると「かつては、筍を採ったり、生活道具の材料にしたりするために少し植えていた程度だったのでは?」 という竹林ですが、ひとたび放置されると、その旺盛な繁殖力で一気に勢力を拡大します。
密生するため地面に光が届かず、下草や低木も生えません。生物の多様性が見込めず、豊かな森には程遠い状態になってしまうわけです。
菅野さんの「筍が生えてくる山に整備して、地域の方が筍を堀りに集まれる場にするのが目標です」と明るく確信を持って語られる表情は頼もしい限りでした。
田畑での作業が地域交流の機会を創出
現在の鹿背山倶楽部の活動ですが、竹林整備の他に、田畑での農作物栽培も行っています。発足当時はもとあった田畑に竹や雑木が繁殖侵入していましたが、木や草を抜き、土を耕すところから始めて、今では毎年、4枚の棚田で古代米などを栽培し、畑では季節ごとにさまざまな野菜を育て、収穫しています。
「タカラ・ハーモニストファンドの助成を活用して発電機と草刈り機を揃えることができました。田畑の整備段階はもちろん、作物を栽培する際にも、農作業は雑草との闘いの連続。これらの機械が大いに活躍しています」と菅野さんは話します。
米は苗床作り、播種、代かきと田植え、夏場の除草、稲架作りと稲刈り、脱穀・籾すり、収穫したもち米での餅つきと、地域の新旧の住民の方が協働して取り組んでいるのだとか。 また、畑では地域の小学生に芋掘りなどの農業体験の機会を提供しています。
 手作業による田植えの様子
手作業による田植えの様子 白菜などの冬野菜が元気に育っている
白菜などの冬野菜が元気に育っている
新しい街 けいはんなで、里山を再生する意義
鹿背山倶楽部では、木津川市の広報誌で定期的に参加者を募っています。 「里山を再生し自然環境を保全する活動は、自らにもかけがえのない充実をもたらします。ぜひ、定年退職した方をはじめ、幅広い世代の方に参加していただきたいですね」と語る菅野さん。
一方で、地域の子育てサークルの親子参加や、小学生の農業体験の受け入れなど、新たな展開も広がっています。子どもたちが地元の自然に愛着の思いを抱くきっかけづくりが積み重ねられています。
 小学生の農業体験の様子
小学生の農業体験の様子 収穫したもち米での餅つきは年末の恒例行事に
収穫したもち米での餅つきは年末の恒例行事に