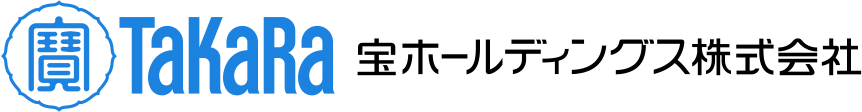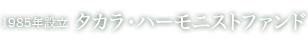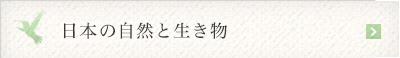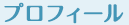2017.03.14
宍塚の里山を守り、未来につなげる活動に取り組む
認定NPO法人 宍塚の自然と歴史の会
2016年11月に茨城県土浦市にある認定NPO法人・宍塚の自然と歴史の会を訪問。代表の及川ひろみさんに、具体的な活動内容や活動にかける思いについて伺いました。
「宍塚の里山を守りたい」という思いから始まった里山活動
「ここは繁華街や住宅街からも近くて気軽に足を運べるにもかかわらず、一歩足を踏み入れると豊かな自然が広がり、歴史的な遺跡群も豊富に点在する。本当に奇跡のような場所なんです」。
及川さんは、お子さんが小さい頃はしばしば家族で遊びに来て、宍塚の自然に親しんでいたそうです。しかしあるとき、愛着をもっていたこの里山が開発されることを新聞で知ります。手近なのに多彩な自然が残り、子どもも大人も容易に自然に触れあえる貴重なこの場所を守り、次世代に引き継いでいきたいという強い思いから、及川さんは保全活動に動き出します。宍塚の自然について新聞に寄稿したり、保全に協力的な研究者や地元の人とつながりを作るなど、約2年間、地道に活動をしていたころ、つくば青年会議所で開催されるシンポジウムで「宍塚の里山の魅力や自身が抱く熱い想いを伝えてほしい」と講演を依頼されます。1989年、この講演をきっかけに及川さんは『宍塚の自然と歴史の会』を発足し、活動をスタートさせました。
科学的な自然調査に裏付けられた保全活動
その後、里山の開発計画はなくなったものの、環境や暮らしの変化により状況は少しずつ変化していきます。それまで当たり前にあった自然が、住宅地の広がりで少しずつ減っていくのを目の当たりにする中で、「貴重な宍塚の里山を次世代に引き継ぎ、さらに未来に残したい」――里山の保全活動を始めるきっかけとなった及川さんの思いがこの会がめざす思いとなり、本格的な活動を開始しました。
宍塚を残すための最適な方法は何か。考えた結果、専門家のサポートを受けた本格的な「自然調査」によって、里山の現状を知り、保全方法を模索するという方法に辿り着きました。
例えば、池の様子が変わったと感じたときは「何を調査すべきなのか」を専門家に相談し、池にいるプランクトンを調べるなど、保全対象としている宍塚の里山について科学的に検証を行っています。
発足から数年後には自分たちの学びも兼ねたサミットを3回開催しました。各回とも環境保全で著名な大学教授や、遠くは沖縄からも専門家を招きました。
また会の活動や里山の「今」を伝える会報『五斗蒔だより』は設立翌年から発行を開始し、今も地元の方々や小学校、公民館、全国各地にいる会員に届けられています。自然ななりゆきで発足した会が、地域をはじめいろいろな人を巻き込んで27年もの長きにわたり活動が続いていることに、私たちは深く感銘を受けました。
豊かな里山を次世代に引き継ぐために

「未来を担う子どもが自然を好きでなかったら、この先、自然は残りません。里山は人の心を育てる場所なんです。自然の中で過ごした楽しい思い出が、子どもや若い人の心に残っていけば、きっとあとにも続いていくはずです」。
会では保全活動を進める一方で、子どもを対象にしたさまざまなイベントに力を入れています。例えば、主催イベント「里山子ども探偵団」は、里山での遊びを知らない街の子どもが、気軽に自然とふれあえる場として地域でも人気の活動だそうです。
「最初は虫も触れなかった子どもが、遊び方を教えると帰る頃には夢中になって虫を捕まえているんです。中学の頃に参加していた子が大人になって再び来てくれたということもありました」。
子どもの様子を話す及川さんはとても嬉しそうです。ここで、里山で過ごす楽しさや自然の魅力を知った子どもたちが、「自然を残したい」という思いを強くし、将来的に会の思いを繋いでくれることを及川さんは期待しています。
発展を続ける田んぼの活動
平成17年度のタカラ・ハーモニストファンドからの助成金は、当時取り組み始めたばかりの田んぼ活動に使われました。当初、地元の農家さんに指導を受けつつ無農薬での稲作に四苦八苦していたのが、現在では家族で米作りを体験できる「自然農田んぼ塾」などに発展。
「冬期湛水不耕起栽培に取り組んだことで、減少していたカエルの卵が前年に比べ6倍に増え、また最近ではSRI農法という新たな方法にも挑戦しています」。
試行錯誤を繰り返しながら継続的に田んぼ活動に取り組み、それが里山保全にもしっかりと繋がっている。これは大変意義のあることです。
宍塚、さらには日本中に残る自然に対する思い
現在、会員は北海道から沖縄まで全国各地に約480人。2010年には、日本文化を未来に伝える活動をする団体として、ユネスコの「プロジェクト未来遺産」にも登録されました。近年は主要メンバーに30代の若手が入り、会の運営もますます活性化しています。「人の輪が広がって活動も大きくなりましたが、保全活動は宍塚だけの問題ではなく、日本全体の問題でもあります。これからは今まで宍塚で実践してきた里山保全のしくみを、全国的に広めていきたいと考えています」。