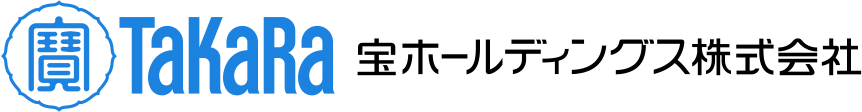「宝焼酎」のおいしさを支える“真っ白なキャンバス”とは。限りなくピュアなアルコールづくりへのこだわりを探る!
2025/02/28
<目次>
常に高い品質を保ち、ピュアなアルコールを安定的につくることが使命
-

「甲類焼酎」と聞いて、あなたはどのようなイメージを思い浮かべるだろうか?
「無色透明」「チューハイ(サワー)などのベースに使われる酒」…いずれも正解だが、数多ある酒類の中で「甲類焼酎」ほど印象が薄い酒はないかもしれない。そんな「甲類焼酎」で国内トップシェアを誇るのが、「宝焼酎」ブランドを有する宝酒造だ。
ロックや水割りで飲む時はまろやかに、チューハイのベースとした時は、割材の味をいかしながらも焼酎の味がしっかりと感じられる。そんな「宝焼酎」ならではの味わいは、「連続蒸留したピュアなアルコール」と「樽貯蔵熟成酒」のブレンドの妙によりうまれる。
「宝焼酎」の誕生は1912(大正元)年。当時の「宝焼酎」は、連続蒸留したアルコールに加水し、酒粕を原料に蒸留した焼酎(粕取焼酎)をブレンドしていた。それまでの焼酎にはない軽快な口当たりとまろやかな芳香は、大変な人気を博したという。
この、“ブレンド”をして「宝焼酎」の味わいを設計するというこだわりと技術は、100年以上たった現在も受け継がれ、磨かれ続けている。宝酒造には、松戸工場(千葉県)、楠工場(三重県)、島原工場(長崎県)と3つのアルコール製造拠点がある。今回は、その中で最大規模を誇る松戸工場にお邪魔して、生産管理部製造課 専門部長の佐々木秀男に、同社のアルコール製造のこだわりや高品質の秘密を聞いた。
「私たちの使命は、純度の高いピュアなアルコールをつくること。それに加えて、最終製品になったとき仕上がりにブレがでないよう、高い品質レベルを一定に保ち続けることです」
そう話すのは、1991年に入社して以来30年を超えて宝酒造のものづくりに携わっている、生産管理部製造課専門部長の佐々木秀男。島原と松戸の2工場で研鑽を積んだ蒸留のエキスパートだ。
松戸工場で日夜生産されるアルコールは、主に宝酒造の東日本向けの製品に使われている。
ピュアかつ高品質なアルコールづくりにこだわるのには理由があるという。「私たちが製造しているアルコールは、『宝焼酎』に代表される甲類焼酎をはじめ、『タカラ焼酎ハイボール』などRTD※の酒類から『タカラ本みりん』などの調味料まで、宝酒造が造る多種多様な製品のベースになっています。また当社は、他の酒類・食品メーカー等にも原料としてアルコールをご提供しています。お客様に安定した味わいとおいしさをお届けするためには、それらのベースとなるアルコールの純度や品質を、常に高く保つ必要があるのです」
※ Ready to Drinkの略。缶入りチューハイなどそのまま飲むことができるアルコール飲料のこと
そもそも、「甲類焼酎」とは?
-
酒類は、「醸造酒」と「蒸留酒」に大別される。「醸造酒」は、穀物や果実などの原料を酵母によりアルコール発酵させた酒の総称である。清酒(日本酒)、ビール、ワインなどが該当する。そして、醸造酒を蒸留してつくる酒が「蒸留酒」だ。
「蒸留」とは、原材料を発酵させてつくったアルコールを含んだもろみ(発酵液)を、蒸留機で沸騰させ、蒸発した気体を冷却することで、アルコール度数の高い液体を抽出する作業だ。日本を代表する蒸留酒が「焼酎」である。
焼酎はさらに、「甲類」と「乙類」に分けられる。二つの大きな違いは、蒸留方法とアルコール度数である。
「単式蒸留機」と呼ばれる蒸留機で一度だけ蒸留したものは「本格(乙類)焼酎」となる。主原料には、米や麦などの穀類やさつまいものほか、そば・黒糖などさまざまな原料が使われる。素材の特徴がいきた、個性豊かな味わいが魅力だ。酒税法で、アルコール度数は45度以下と規定されている。そして、「連続式蒸留機」で蒸留したものが「甲類焼酎」だ。主原料となるサトウキビ糖蜜を原料とするアルコール含有物を、連続式蒸留機の「蒸留塔」に連続して供給し、複数本の蒸留塔で蒸留を繰り返す。その過程で不純物を取り除き、純度の高いアルコールができあがる。それに割水(加水してアルコール度数を調整)し壜詰めしたものが、一般的な「甲類焼酎」となる。こちらは、アルコール度数が36度未満と規定されている。
十数本の蒸留塔を有する松戸工場の蒸留機。最も高い塔は約35m、12階建てビルに相当する高さ
科学的分析と人による分析で品質管理を徹底
-
「宝焼酎は、真っ白なキャンバスに一滴の絵の具を垂らしてできている」
―宝酒造でアルコール製造に携わるスタッフの間で引き継がれている言葉だ。真っ白なキャンバスとは“ピュアなアルコール”を、“一滴の絵の具”とは宮崎県にある同社の焼酎蔵・黒壁蔵で製造している「樽貯蔵熟成酒」を指す。キャンバスがきれいでないと一滴の絵の具の色が鮮やかに表現できない。
すなわち、ピュアなアルコールの品質に細心の注意を払わなければならない、ということを言い表している。ピュアで高品質なアルコールを生み出すには、徹底した品質管理が必要不欠という。
「サトウキビ糖蜜を原料とするアルコール含有物を連続蒸留するのですが、農産物由来の輸入原料であることもあり、どうしてもばらつきがあります。品質を一定に保つには、『このような性質だから、こういう条件で蒸留塔を操作しよう』など、日々新しく入ってくる原料の不純物の組成や濃度を分析し、その品質に応じて、細かく蒸留をコントロールしなければなりません」
管がひしめきあう蒸留設備の内部
「また、渋みや辛さに関係する雑味成分などの不純物は、微量であっても最終製品の品質を左右します。極限まで雑味がなくピュアなアルコールにするため、製造プロセスのあらゆるタイミングで、品質チェックを実施しています。ガスクロマストグラフ(GC)という分析計測機器を使って蒸留途中の液を抜き出し不純物の濃度を測り、当社で規定している厳しい基準値をクリアできているかを入念に確認します」
ガスクロマストグラフで、不純物濃度を計測し分析する
計測器を使って科学的分析をクリアしたサンプルは、佐々木たちプロフェッショナルな“人”によりダブルチェックを受ける。「最後は人の嗅覚による“官能(かんのう)評価”と呼ばれる手法で、当社が基準としているものと差異がないか、異臭がないかなどを確認します。この“官能”については何度も研修を重ねたスタッフが実施しています。精密な機械と人の厳しいチェックによって、宝酒造の製品としてふさわしいアルコールとしてようやく認められるのです」最後は人が香りや異臭を確認する“官能”評価でチェック
“真っ白いキャンバス”の意味について問うと、佐々木は次のように語った。
「私の理解では、真っ白とは『無、何もない』ということ。『宝焼酎』のおいしさの秘密は、我々がつくり出すピュアなアルコールと、黒壁蔵で製造し、多彩な風味を付与する樽貯蔵熟成酒のブレンドの妙にあります。ベースとなるアルコールに少しでも臭いがあったりすると、樽貯蔵熟成酒の風味がマスキングされ損なわれてしまうのです。無であることが大事ではあるものの、樽貯蔵熟成酒だけを味わうわけでなく、ベースを支えるアルコールの品質がしっかりしていないと、おいしい『宝焼酎』にはならないのです」
科学的分析と人による分析を経て完成した“真っ白なキャンバス”であるピュアなアルコールは、さまざまな宝製品となり、飲食店やお客様の食卓を彩っているのだ。
高品質を叶えるため、“ハード”だけではなく“ソフト”も育成
-
業界屈指の品質の高さを誇る宝酒造のピュアなアルコールには、設備、蒸留技術、そして、それらを熟知しコントロールする“人”の存在も重要だ。
言われた操作を指示通りにやる段階から、蒸留をひと通り経験して、状況に合わせ正確に自己判断ができるようになるためには、6~7年はかかると佐々木は言う。相応の経験値が必要となるため、人材の育成にも力を注いでいるという。
「現在蒸留には、若手からベテランまで、11名の技術スタッフが携わっています。蒸留塔は、年末年始、ゴールデンウイーク、お盆休み期間以外はフル稼働で、24時間体制で厳しく管理し、常に変化を見ながら対応しています。蒸留棟では、危険物を取り扱うので、細部にまで気を遣います」
「これからも安定的に日々異なる環境に最適な対応をして行くために、業務と並行して、若い世代への技術の伝承も大切だと考えています。ピュアなアルコール造りには、原材料の状態や、温度・圧力・流量の変化など、つど状況に合わせた判断が必要になってきます。蒸留塔の操作方法などの技術の継承は、日々の実務を通じて行っています。加えて、近年では、手順書や対応策などを記した記録をデータ化し、培った技術や知見といった貴重な情報を検索しやすくするなどして、未来に繋ぎたいと考えています」
設備のハード面と人や日々の運用といったソフト面の進化には、現場で活動するメンバーの声が反映されている。
「工場全社員参加型の自由な提案制度があり、自分たちで色々なアイデアを出して取り組みを推進しています。作業の効率化や安全性の向上はもちろん、最近では省エネルギーの視点が大切です。蒸留には沢山のエネルギーを使います。例えば、蒸留時に排出している熱を回収して再利用するなど、高品質を維持したまま、少しでもエネルギーを削減できる工夫を考えながら、品質だけでなく地球環境にもこだわったものづくりをしています」
ピュアなアルコールは、宝製品のおいしさを支える絶対的名脇役
-
「松戸工場で働くメンバーは皆、お客様がどのように楽しんでいただけるのかを思いながら、愛情を持って製品づくりをしています。だから私たちの製品を楽しんでもらっている光景を見ると、本当に嬉しい。ピュアなアルコールは、脇役かもしれません。しかし、『宝焼酎』をはじめ自社の色々な製品を支えており、その品質が製品にあたえる影響はとても大きい。これからも安心でおいしい製品をお届けするために、まずは、そのベースとなる純度の高いピュアなアルコールをしっかりとつくり続ける、という役割を果たしていきたいと思います」
このように熱い想いを語る佐々木に、最後に『宝焼酎』のオススメの飲み方について教えてもらった。
「甲類焼酎というと一般的に無味なイメージがありますが、バラエティに富んだ『宝焼酎』ブランドの味わいの決め手となる“樽貯蔵熟成酒”の持ち味をいかし、引き立てるのは、限りになくクリアでピュアなアルコールを活用しているからこそ、です。また、ピュアだからこそ、いろんな飲み方できるのも魅力。私自身は炭酸で割ってレモンを入れるのが好きですが、お湯で割ってもお茶で割ってもおいしいので、ぜひお好みの飲み方で楽しんでいただきたいです」
“真っ白なキャンバス”と例えられるピュアなアルコールを感じながら、あなたならではの“おいしい飲み方”を発見してみてはいかがでしょうか。
製造しているピュアなアルコールが使用された極上<宝焼酎>と記念撮影
※次回は、“一滴の絵の具”である、宮崎県・黒壁蔵での樽貯蔵熟成酒づくりについてご紹介します。